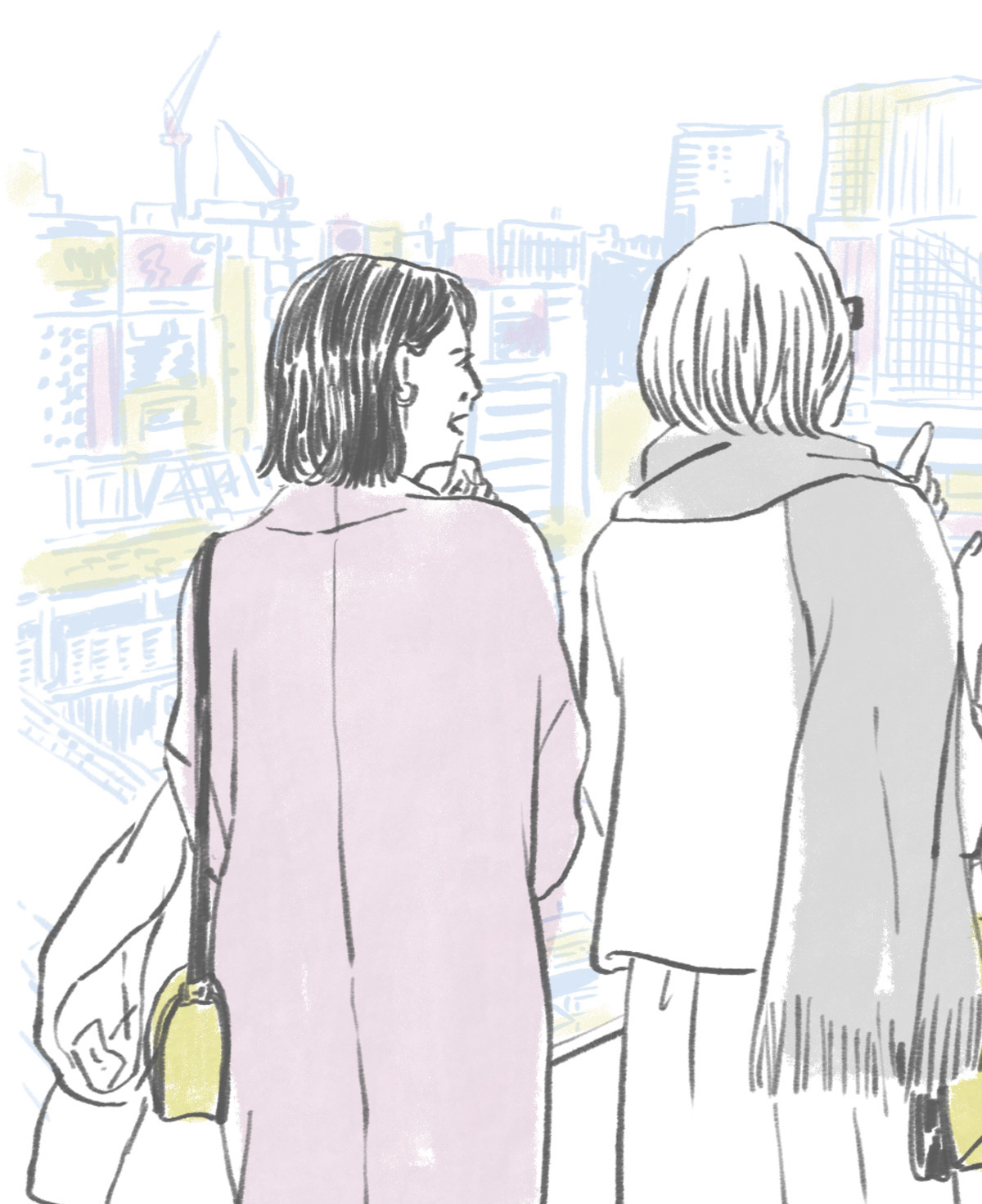
第4話「変わることも奇跡、変わらないことも奇跡」
「ねえ、あれ、トシヤくんじゃない?」
宮下パークを散策し終えて、ヒカリエに着く直前だった。
隣を歩く京子がショップバッグを軽く持ち上げると、その手の先で、人混みの隙間から歩道橋を駆け上がる男の子の背中が見えた。
「ええ? そう?」
「あんた、母親でしょ? 後ろ姿でわかりなさいよ」
「いやあ、もう一緒に住んでないからさ」
じっと目を凝らす。アウターは見覚えがないけれど、足元の靴や走り方は、確かに俊哉っぽい。
「言われてみれば、そう見えるけど。似た人じゃない?」
「あんな髪型、そうそういないと思うけど」
「あれ、襟足、青色?」
「うん」
「そっかあ。まあ、ここ、渋谷だし。青色の髪の似た人もいるんじゃない?」
「ええ? 絶対トシヤくんだったけどなあ。あんた、もうちょっと息子に興味持ちなよ」
京子は少し残念そうな顔をする。そう言われてもなあ、と思う。
俊哉は、三年前に一人暮らしを始めて以降、正月にしか帰ってこなくなった。元から親離れが早かった印象がある子だったけれど、22で家を出るとは思わなかったし、ここまで交流が途絶える関係になるとも、さすがに予想していなかった。
同じ都内に住んでいるのに、息子がどこで何をしているのか、全く把握していない。
「警察行くところだったりして」
冗談めかして、そう言ってみる。
「え、なんか悪さ、したの?」
「冗談。多分そんな度胸ないから。うちの子」
それだけは、妙に自信があった。どれだけ人間関係が変わったとしても、あの俊哉はきっと、警察にお世話になるような悪事には手を染めないだろう。昔からだらしないところは多かったけれど、正義感だけは、妙に強い子だったから。

渋谷ヒカリエのエントランスをくぐると、暖房が体中を包んで、羽織っていたアウターを柔らかくする。冷えには昔から弱かったが、ここ数年はさらに、体に応えるようになった。
寒かったねえと言いながら、京子とくだりエスカレーターを目指して歩く。久しぶりにヒカリエに入ったので少し店内を見て回りたかったが、京子は寄り道を許さぬ気配で、目的地の地下2階までまっすぐに進もうとしている。
「トシヤくん、いくつになった?」
エスカレーターに乗ると、京子が振り向いて言った。
「25だね」
「もうそんなになったの!」
親である私ですら、同じ気持ちだった。小さかった時期は大変で、あと何年子育てが続くのだろうと途方に暮れていた。けれど、振り返ってみればあっという間すぎて、これならもう少し成長の過程をじっと見守っていたかったとすら思う。
「あんたもいろいろあったけど、よかったね、きちんと大きくなって」
「きちんと、なのかはわかんないけどね」
笑ってそう言うと、いいのよ、元気に渋谷を走ってるんだから、と京子は言った。
スイーツコーナーでお目当ての洋菓子を購入すると、エレベーターに乗って、9階に向かう。そこで京子の弟さんが大規模な展示イベントを開催しているらしく、差し入れを買ってから行こうと誘われたのだった。
「そのお菓子、有名なの?」
フランス語だろうか。洋菓子の袋に書かれたブランド名を読むことができない。エレベーターは貸切状態で、私たちは会話を止めることなく9階を目指している。
「あー、なんか雑誌に載ってた」
「そうなんだ。でも、会場と同じビルで差し入れ買うのってどうなの?」
「いいのよ、ほんの気持ちなんだし」
「その気持ちの問題だから言ってるんだけど」
ふふふ、と笑う。それで済まそうとするのが、京子の悪いところであり、私が好きなところでもあった。
9階に着いて、エレベーターの扉が開く。さっきまでいた洋菓子売り場とはまるで空気が違っていて、静かで、厳かな空気があった。美術館にでも来た気分だ。歩いているお客さんも、どこかシュッとしているし、結婚式帰りの若い女性までいる。
「ヒカリエができた頃ってさ、まだあんた、離婚してなかったんじゃない?」
京子が突然言った。
「どうして?」
「いや、さっき看板でヒカリエ10周年って書いてあったから」
「ああ、なるほど」
10年前は、確かに私はまだ、前の夫と婚姻関係にあった。
「10年前かあ、懐かしいな。あの頃の私、元気だったな」
「いや、今の方が全然元気そう」
「そお?」
離婚したのも、子供が巣立ったのも、ここ10年の話だ。当時はエネルギーがあったから、離婚もできたのだと思う。でも、京子に言われてみて、確かに最近の私はずいぶんと身軽になったと実感する。
「この10年で、渋谷も私たちも、ずいぶん変わったねえ」
京子が9階からの渋谷の景色を眺めながら言った。
「ね、最近の渋谷、全然道がわからないもん」
「すっかりおばさんだ」
「本当に。それでも変わらずこうやって遊んでるんだから、よっぽど奇跡だよね」
高校時代から一緒に遊んでばかりいた京子とだからこそ、このやりとりがやけに沁みるのだ。当時も今も、私たちは変わってない。
「変わることも奇跡、変わらないことも奇跡」
そう呟くと、何それ?と、京子が茶化して笑った。
なんでもない、と私は返す。外に出れば、まだ冷たい冬の風が吹いていることだろう。
それまで、これから展示を楽しむ間は、この温かい気持ちのままでいたい。そう思った。

illust : naohiga
*この小説はフィクションです。実在の事象とは異なることがあります。

 最新情報はこちら
最新情報はこちら



